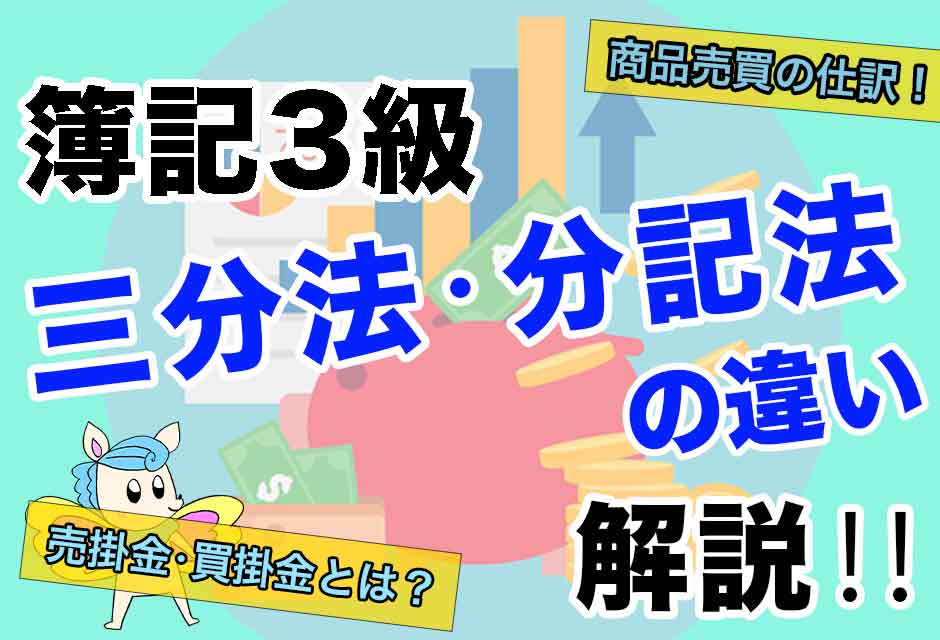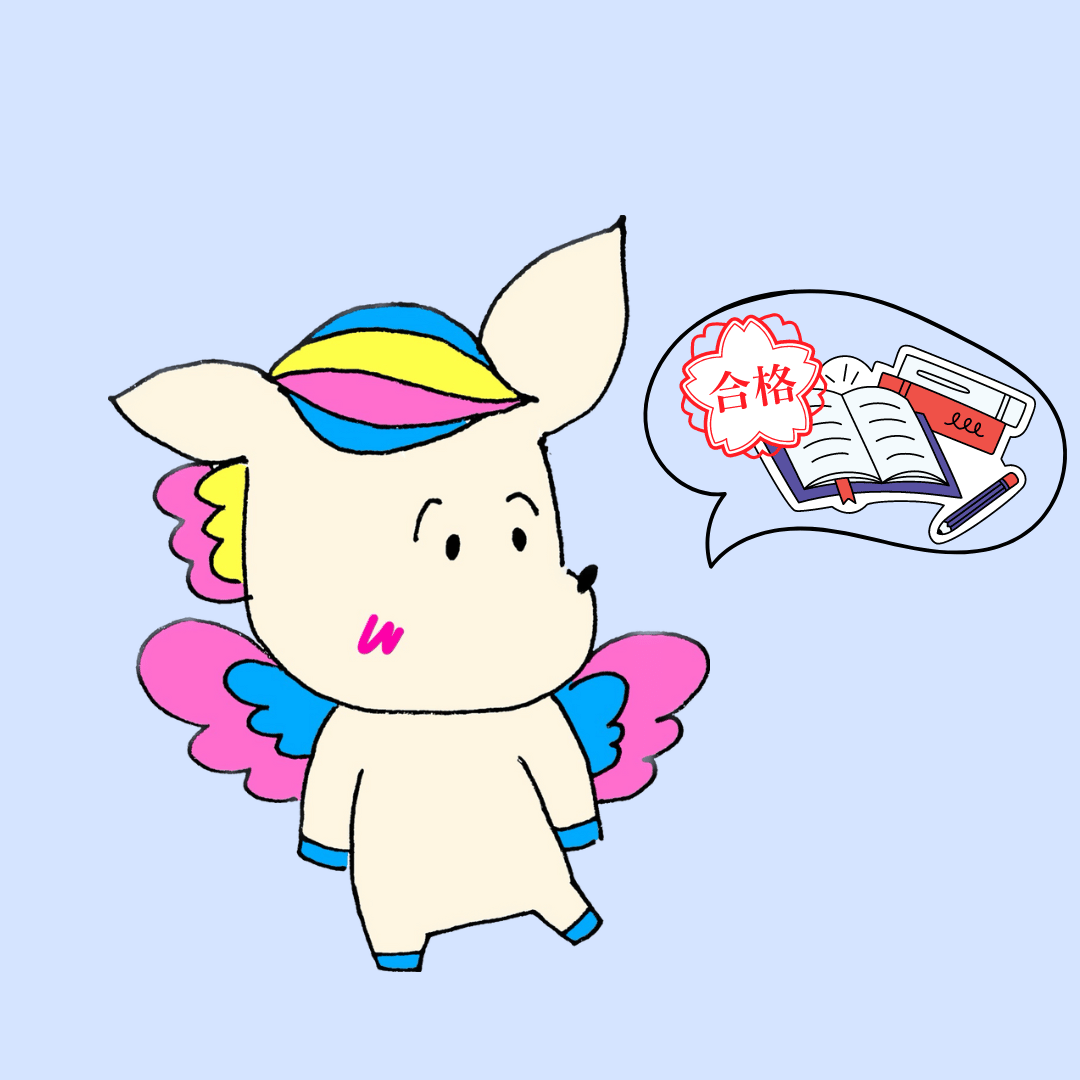簿記3級講座の第二回では、三分法と分記法の違いについて解説していきます。
第一回の講座では、仕訳とは「取引を記録する上で一番基本となる作業のこと」で簿記3級というよりも、簿記自体の基本中の基本となる作業のことだと解説しました。
簿記3級合格までを4ステップに分けた内の1ステップ目が仕訳のマスターです。仕訳をしっかり理解していると、試算表や精算表、財務諸表の作成も躓くことなく、スラスラ進めるでしょう。
第二回目の講座では、仕訳を理解するのに一番イメージのしやすいであろう商品売買に関する仕訳を取引例を用いて解説していきます。
商品を仕入れるときや、売り上げた時の取引があった時の仕訳には、三分法と分記法2種類の仕訳があり、簿記3級では「三分法で処理しなさい。」と指定されていることが多いので、分記法との違いをしっかり理解しておきましょう。
仕訳を行う際重要な、5つの要素や仕訳のルールについて「あれ、なんだっけ?」という方は第一回の講座に戻ってさらっと復習してから始めましょう。
第二回の講座では以下の3つの取引での仕訳を解説することで、理解を深めていきますので全部分かる人は飛ばしてOKです。それではやっていきましょう!
合わせて読みたい
-

-
Udemyで基本情報技術者試験合格を目指す!おすすめ講座5選!
続きを見る
- A商店は仕入れのために、B商店から商品1000円分を購入した。代金は現金で支払った。
- A商店は仕入れた1000円の商品を2000円で売り上げた。代金は現金で受け取った。
- A商店は商品1000円分仕入れた。代金は掛けとした。また、商品の配送料が100円かかったので当店で負担し、配送料は現金で支払った。
商品売買の仕訳で三分法と分記法の違いを理解しよう!
商品売買とは、お店に並べる商品を購入する(仕入れる)ことや、営業していて商品を売り上げたりすることです。商品売買の仕訳をする時、三分法と分記法の2種類の仕訳方法が存在します。
三分法では、費用と収益を使って仕訳を行う方法のことで、分記法では資産と収益だけを使って仕訳を行う方法です。
言葉だけだと分かりづらいかもしれませんが、安心してください。以下を読んで頂くことでしっかり理解できるようになるでしょう。
ちなみに、簿記3級では三分法がよく使われます。
そのため、三分法と分記法の違いを理解をしていないと、試験本番に「三分法で仕訳しなさい」と指定されて焦っちゃったなんて声も聞いていますので、それぞれの違いを理解しておきましょう。
商品を仕入れる取引で仕訳のルールを復習
取引①:A商店は仕入れのために、B商店から商品1000円分を購入した。代金は現金で支払った。
まずは仕訳のイメージを再確認するためにも、商品を仕入れる時の取引で仕訳を行っていきます。
仕入れとは、「自分の店で売る商品を準備(購入)すること」です。
取引①では、商品を1000円で購入して(仕入れて)いるので、商品(資産)が増えています。そして、代金を現金で支払っているので現金(資産)が1000円減っています。
仕訳のルールによると、資産が増えたときは借方、資産が減ったときは貸方に記入するので今回は、「商品」は「資産」なので「借方(左側)」に記入します。逆に、支払った代金「現金(資産)」が減るので「貸方(右側)」に記入します。
ここで躓くようであれば第一回の講座に戻って復習しましょう。
したがって、仕訳結果は
(商品) 1,000円 (現金) 1,000円
となります。
しかし、上記は分記法での仕訳で、三分法では商品(資産)の代わりに仕入(費用)の勘定科目を用いて仕訳を行います。
三分法で仕訳を行った場合は
(仕入) 1,000円 (現金) 1,000円
となります。
仕入れだけの仕訳だとちょっと分かりづらいので、ここでは「ふーん。なんか違う方法もあるんだ〜。」くらいの認識でOKです。以下で掘り下げてイメージを深めていきましょう。
仕入れから売り上げるまでの取引で三分法と分記法の違いをイメージしよう
取引②:A商店は仕入れた1000円の商品を2000円で売り上げた。代金は現金で受け取った。
三分法と分記法の違いをイメージするには、仕入れた商品を売り上げた時の仕訳を行ってみるのがわかりやすいです。
取引②を見ていきましょう。先程仕入れた商品を誰かが購入してくれました。1,000円で仕入れた商品が2,000円で売れたので利益が発生していますね。この取引の仕訳を三分法、分記法それぞれで行っていきます。
三分法で仕訳を行う場合
三分法は、費用と収益、繰越資産の3つで仕訳する方法です。
取引②の場合、最終的にA商店では現金(資産)2,000円が増えて、売上(収益)2,000円が発生しています。
したがって、現金(資産)2,000円が増えているので借方に記入。また、売上(収益)2,000円が発生しているので貸方に(売上)2,000円を記入して、仕訳完了です。
よって仕訳結果は
(現金) 2,000円 (売上) 2,000円
となります。
三分法では、費用と収益で仕訳を行うので、仕入れた商品が減っているからといって貸方に商品を記入する必要はありません。
分記法で仕訳を行う場合
一方分記法では、資産と収益を用いて仕訳を行う方法なので、まずはA商店が取引②で増減した資産に注目します。
A商店がこの取引で最終的に手にしているのは、現金(資産)2,000円が増えて、1,000円で仕入れた商品(資産)が減っています。
そして、1,000円で購入したものが2,000円で売れたので、差額が商品売買益(収益)として発生していることに気づくと仕訳ができます。
よって分記法での仕訳は、現金(資産)2,000円が増えているので借方に記入。商品(資産)1,000円が減って、商品売買益(収益)1,000円が発生しているので貸方にそれぞれ記入します。
仕訳の結果は
(現金) 2,000円 (商品) 1,000
(商品売買益) 1,000円
となり、しっかり借方と貸方の金額が一致していることを確認しましょう。
商品売買で知っておきたい用語を理解
取引③:A商店は商品1,000円分仕入れた。代金は掛けとした。また、商品の配送料が100円かかったので当店で負担し、配送料は現金で支払った。
商品売買の仕訳をする上で覚えたい、一般の人が聞き慣れない言葉を紹介しておきます。
取引③を見ていきましょう。「代金は掛けとした」と見慣れない言葉や、「配送料」などどう処理すればいいかわからないものが出てきます。用語の解説をしながら実際に仕訳を行っていきましょう。
買掛金と売掛金
支払いに関して、掛けと呼ばれる制度があります。平たく言うと「後払い制度」です。
A商店から見て、仕入れる時に掛けにするのが買掛金(かいかけきん)、売り上げた時に掛けにするのが売掛金(うりかけきん)です。
買掛金は、あとから支払う約束をした債務であるので、負債として処理します。一方売掛金は、あとからお金がもらえる債権なので、資産として処理をします。
取引③では仕入れの際に代金を掛けとしているので、買掛金(負債)が増えていることになります。
仕入諸掛りと売上諸掛り
商品を仕入れる時や売り上げた時、配送料や手数料のような細々した費用のことを仕入諸掛り(しいれしょがかり)や売上諸掛り(うりあげしょがかり)と呼びます。
取引③の場合、仕入れの際に配送料が100円発生しているので、仕入諸掛りが発生していることになります。
仕入諸掛りが発生しているときは、三分法での処理の場合、仕入に仕入諸掛りの金額を加算して記入します。
売上諸掛りが発生した場合は、発送費(費用)として処理を行います。
取引③の仕訳の場合は、仕入れた時の1,000円と、配送料の100円で実際に掛かった仕入れ金額は1,100円なので、仕入(費用)1,100円を借方に記入し、買掛金(負債)1,000円が増え、現金(資産)100円が減っているので貸方に記入し、仕訳完了です。
(仕入) 1,100円 (買掛金) 1,000円
(現金) 100円
まとめ
今回は、商品売買の取引例3つで、三分法と分記法の違いについてと、売掛金や買掛金、仕入諸掛りなどの用語についても触れていきました。
まだまだ仕訳の中の基本中の基本ですが、一歩一歩なれていきましょう。
次回からは、現金ではないけれども現金として処理するものを紹介していきます。
- 商品売買の仕訳には三分法と分記法2種類存在する。
- 三分法 👉 費用・収益・繰越商品(資産)の3つで処理を行う仕訳方法。
- 分記法 👉 資産と収益だけで処理を行う仕訳方法。
- 後払い制度のことを掛けと呼ぶ。
- 買掛金 👉商品を購入する時に掛けとした時の勘定科目。負債。
- 売掛金 👉 商品を売り上げた時に掛けとした時の勘定科目。資産。
- 商品の購入や売り上げた際に発生する細々とした費用を諸掛りと呼ぶ。
- 仕入諸掛り 👉 仕入れた時にかかった費用(発送費など)のこと。仕入に加算して処理。
- 売上諸掛り 👉 売り上げた時にかかった費用(配送料)のこと。別の費用として処理。