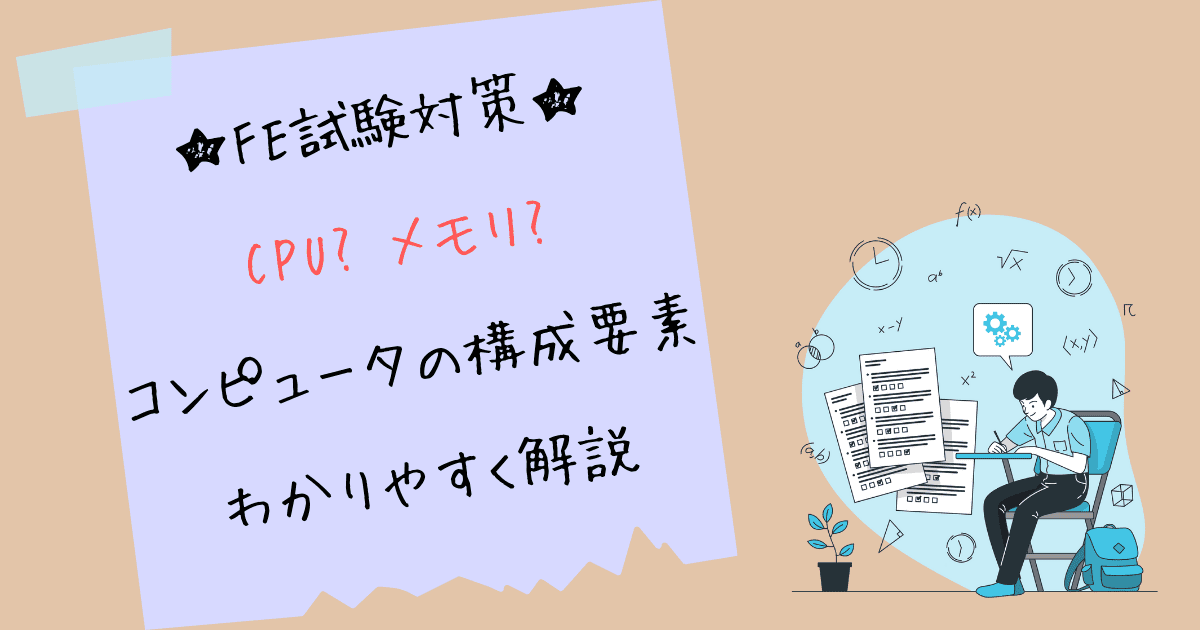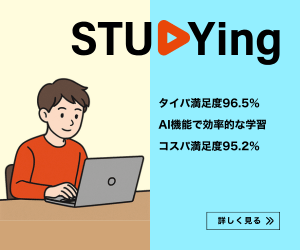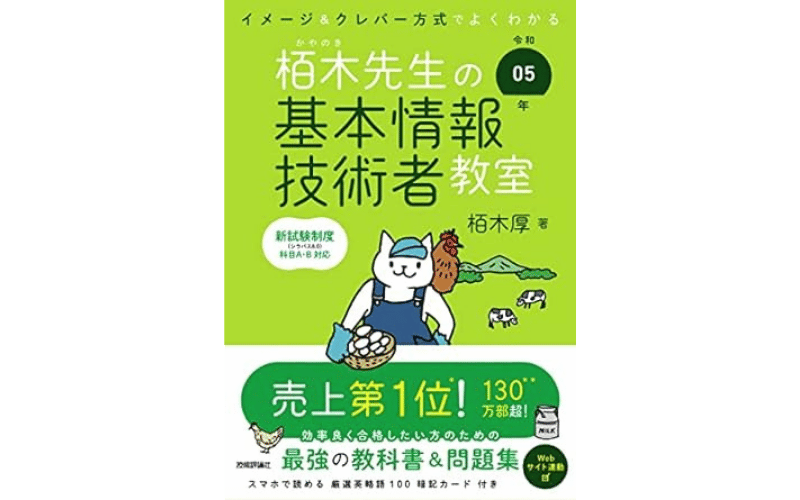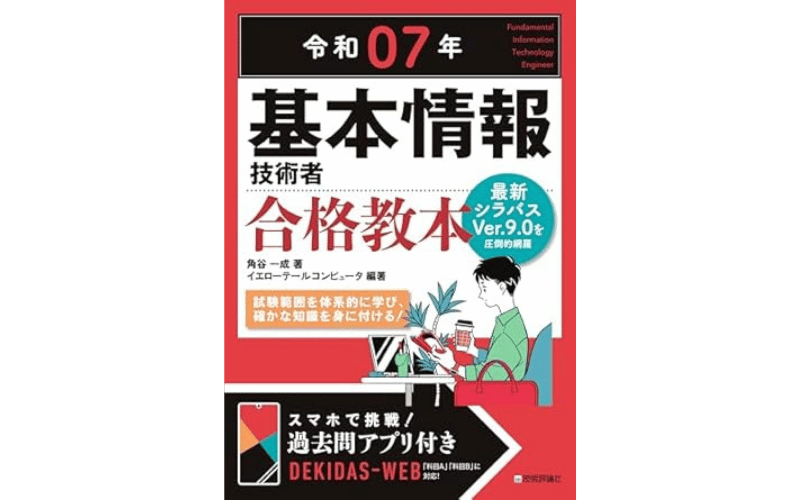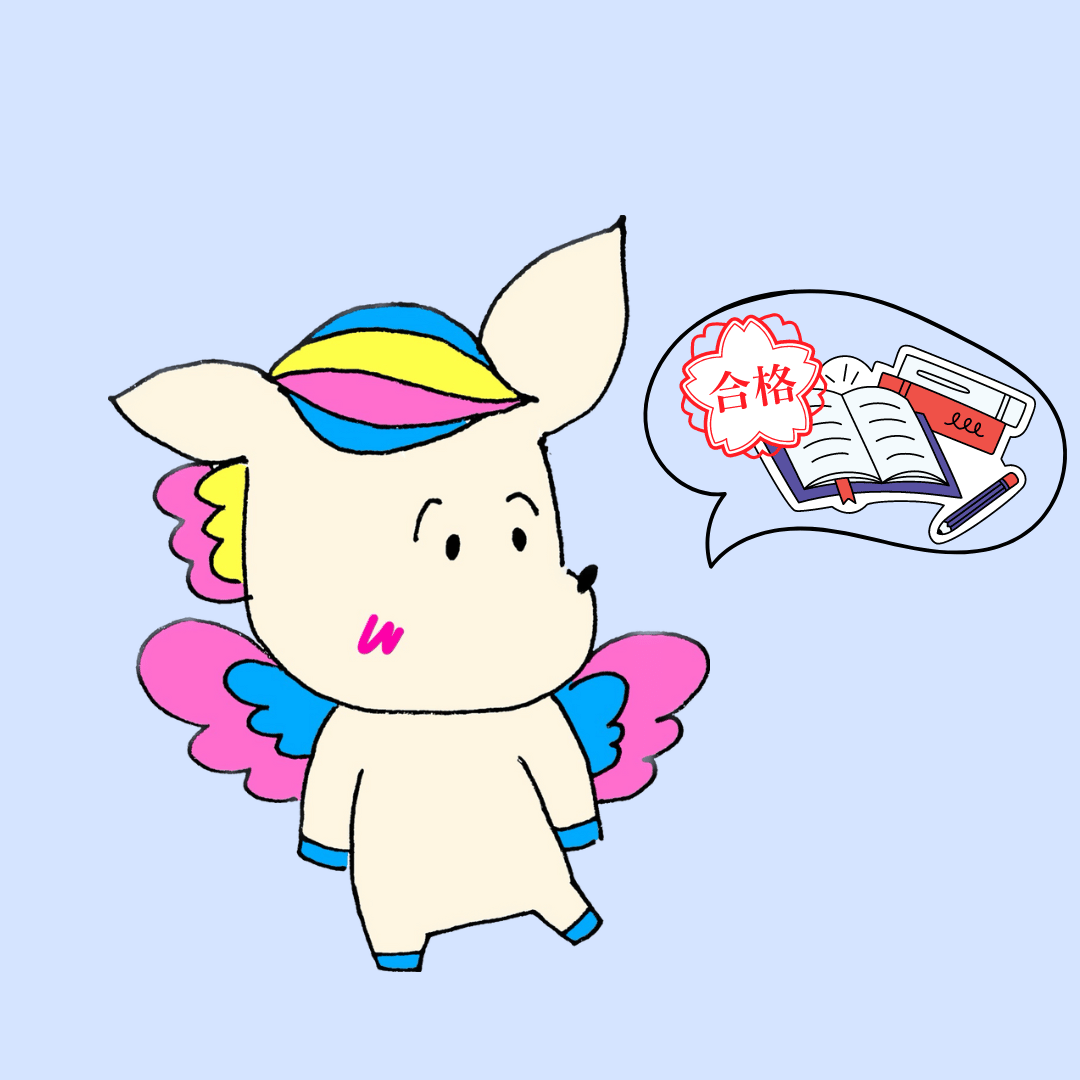この記事で解決できる内容
※タップすると該当箇所までジャンプできます。
「CPU?メモリ?なんか難しそう…」とパソコンやコンピュータを構成する要素がよくわからない人は多いのではないでしょうか?
基本情報技術者試験(FE試験)では、コンピュータの構成要素やハードウェア分野の問題が頻出。特に午前試験ではクロック周波数やアクセス時間などの計算問題も出題され、苦手に感じる人も多いです。
本記事では、CPU・メモリ・補助記憶装置などの役割を図解でやさしく解説しつつ、試験によく出る計算問題や出題傾向にも対応。さらに、**おすすめの参考書・動画講座(Udemy・Bizlearn)**も紹介しているので、「効率よく得点源にしたい!」という方はぜひチェックしてください。
基本情報技術者試験とは Fundamental Information Technology Engineer Examination を略してFE試験と呼ばれています。
IPA(情報処理推進機構)によるとFE試験は以下のように紹介されています。
情報処理技術者試験は、「情報処理の促進に関する法律」に基づき経済産業省が、情報処理技術者としての「知識・技能」が一定以上の水準であることを認定している国家試験です。
IPA(情報処理推進機構)
IT企業への就職や転職を考えている方だったり、これからエンジニアを目指したい方はFE試験を受けてみると良いと思います。
短期間で効率よく合格を目指すなら「スタディング」がおすすめ!
関連記事:【IT登竜門】基本情報技術者一発合格!おすすめの学習方法5選
コンピュータの構成要素とは?5つの基本ブロックを図解で解説
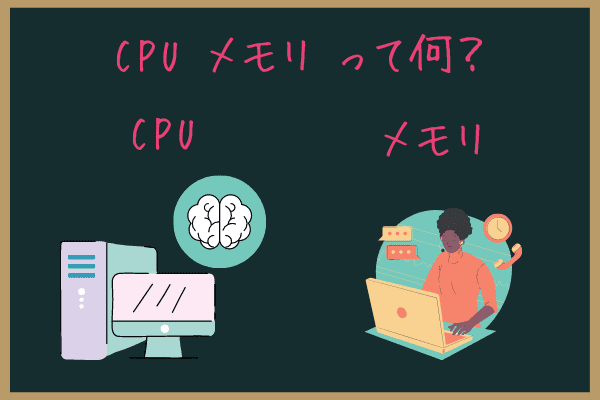
今回はFE試験の午前試験で、たくさん出題されているハードウェアの分野の基礎を解説します。
ハードウェアとは、コンピュータを構成する物理的に触れる部分のことを指します。
例えば、パソコン本体や、マウスやキーボード、メモリやHDDなど実際に触れることができるものがハードウェアです。コンピュータはハードウェアとソフトウェアから構成されています。
ソフトウェアはコンピュータの部品とかではなく、パソコンの中で動くソフトやアプリケーションといった実際にはさわれないもののことです。例えばWordやExcelなどで、これらはマイクロソフトが開発したアプリケーションでパソコンの中で動作するソフトウェアです。
今回はハードウェアについて理解してもらうことでまずはコンピュータの仕組みの基礎中の基礎を理解できるようにしていきましょう。
関連記事:基数とは?10進数から2進数へ変換ができるようになるまで!
コンピュータの構成要素|5大装置とは?
コンピュータには入力・制御・演算・記憶・出力の5大要素から構成されており、5つの装置のことをコンピュータの5大装置と呼びます。5つの装置はそれぞれ以下の通りです。
コンピュータの構成要素
- 入力装置 ➾ データやプログラムを主記憶装置に読み込む装置。
- 制御装置 ➾ 主記憶装置に記憶された命令に従って各装置を制御する装置。
- 演算装置 ➾ 各種の演算を行い、主記憶装置に格納する装置。
- 記憶装置 ➾ データやプログラムを記憶する装置で主記憶装置と補助記憶装置に分けられます。
- 出力装置 ➾ 主記憶装置のデータを外部に出力する装置。
更に制御装置のことをCPUとよんだり、主記憶装置のことをメモリと呼んだりもします。
また具体的なものを上げると、出力装置にはプリンタやディスプレイが、入力装置にはマウスやキーボードが当てはまります。
これらの5大装置を理解することは、コンピュータの構造を理解することに近づきます。
CPUとは?制御機能と演算機能を兼ね備えている
CPUとは Central Processing Unit の略で、わかりやすく言うとコンピュータの頭脳のことです。
コンピュータを購入するときや、調べていると、プロセッサやMPU、処理装置という言葉を目にすることがあるかもしれませんが、これらも全てCPUと同じ意味で使われています。
コンピュータの5大要素の内、制御機能と演算機能を担っており、マウスやキーボードから入力されたデータを演算したり、出力するデータを制御したりする部分です。いわば司令塔のような役割です。
CPUとは??
- コンピュータの頭脳のこと
- プロセッサ・処理装置・MPUなどと呼ばれることもある
主記憶装置(メモリ)とは
メモリとは、コンピュータが一度に処理できる作業量を表したものです。
コンピュータは、「これこれしなさい」という命令を受けてそれに従って処理を行っていますが、命令がたくさんあると一度に実行できる数には限りがあるため、メモリで管理しつつ順番に処理をこなしていきます。
例えばメモリが10GBのコンピュータに同時に11GBのプログラムを実行させようとするとキャパオーバーになってしまいます。つまりメモリとはそのコンピュータの同時処理数を表したものってイメージです。
補助記憶装置(HDD)とは
補助記憶装置(HDD)とは、データやプログラムを外部に記憶するための装置です。磁気ディスク装置やHDD、USBメモリなどが補助記憶装置に当たります。
主記憶装置との違いは、電源を一度切っても記憶が消えないのが補助記憶装置、電源を切ると記憶内容が消えてしまうのがメモリです。そのため、メモを保存したり、Wordで書いた文書を保存したりするときに使用するのは補助記憶装置です。
基本情報技術者試験ハードウェアの問題の特徴
FE試験で出題されているハードウェアの問題には、コンピュータの構成要素である用語がどんな意味を持っているかを問う問題や、CPUの性能を評価するクロック周波数を求める計算問題、メモリのアクセス時間を求める計算問題などが主に出題されています。
コンピュータの構成要素に関してはこれから少しずつ覚えていきましょう。
今回は頻出される計算問題を解説していきます。
基本情報のハードウェア分野によく出る計算問題3選
基本情報技術者試験のハードウェア分野は単なる暗記分野ではなく、意外と計算問題が多いです。「計算問題ってなんか苦手…」「クロック周波数とかアクセス時間とか、用語の意味からつまずく」
このパートでは、基本情報技術者試験に頻出の3大計算問題について、それぞれ「どんな問題が出るのか」「どのように解くのか」をわかりやすく解説します。
基本情報ハードウェア計算問題3選
| 問題の種類 | 概要 |
|---|---|
| クロック周波数 | CPUの性能(1命令の実行時間)を求める |
| アクセス時間 | 主記憶装置と補助記憶の平均アクセス時間を計算 |
| レジスタ・主記憶サイズ | アドレスビット数や記憶容量の求め方 |
それぞれの問題の出題パターン・公式・覚え方のコツまで丁寧に解説しています。「数字が出ると固まってしまう…」という人も、この記事を読み終える頃には得点源に変わるはずです。
関連記事:【基本情報】2の補数とは?2進数で負の数を表す仕組みをわかりやすく図解解説
基本情報技術者試験対策①:CPUの性能を評価するクロック周波数に関する問題
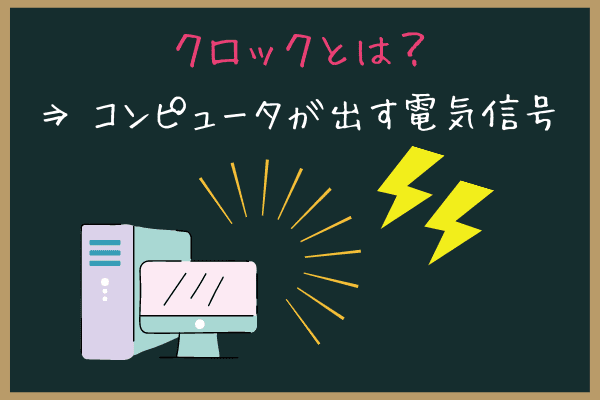
CPUの性能を評価する一つの指標として、クロック信号があります。
クロック信号とは正確な時間間隔を持った電気信号のことで、クロックによって命令したり演算を行ったりしています。
そして1秒間に何回クロック信号を発生させることができるのかを表したものをクロック周波数と呼びます。クロック周波数は ○Hz (ヘルツ)で表現し、クロック周波数が大きいほうが実行速度が速いCPUと言えます。
クロックサイクル時間
クロック信号が発生する時間の感覚のことをクロックサイクル時間と呼び、クロック周波数が1MHzのCPUのクロックサイクル時間は1秒間に1.0×106回のクロック信号を発生させるため、1回クロック信号を発生するのにかかる時間は1000マイクロ秒です。
クロックサイクル時間 = 1秒 / クロック周波数 で求めることができます。
クロック周波数を求める過去問にチャレンジ
1GHzのクロックで動作するCPUがある。このCPUは,機械語の1命令を平均0.8クロックで実行できることが分かっている。このCPUは1秒間に平均何万命令を実行できるか。
令和元年秋期 午前問12
ア. 125
イ. 250
ウ. 80,000
エ. 125,000
解説)
この問題を解くのに必要な知識は、1GHz(ギガヘルツ)がどういう意味なのか、クロック周波数の求め方を知っているかどうかというところがポイントです。
GHz(ギガヘルツ)のギガとはメガの1000倍、メガはキロの1000倍、キロはただ単に1000倍です。
そのため、109倍を表しています。つまり1GHzは1秒間に1.0 × 109回クロック信号を発生させます。
0.8クロックで1命令ができるため、1.0 × 109 ÷ 0.8 = 1.25 × 109回命令ができます。
ココまででなんとなく選択肢は エ ということはわかると思いますが、問題文を読むと「何万回」とあるので 10000 = 104 で割ってあげると、1.25 × 105 = 125,000 とわかります。
よって答えは エ です。
キロ・メガ・ギガ
- キロ(K) ➾ 1000倍(103)
- メガ(M) ➾ Kの1000倍(106)
- ギガ(G) ➾ Mの1000倍(109)
- テラ(T) ➾ Gの1000倍(1012)
基本情報技術者試験対策②:アクセス時間を求める問題
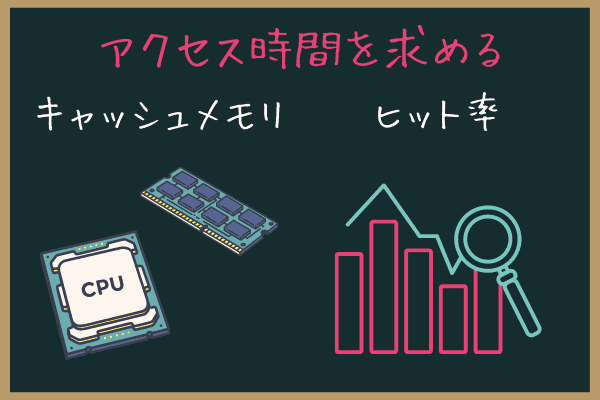
FE試験でハードウェアで出題される計算問題といえば、クロック周波数とこのアクセス時間を求める問題くらいです。
インターネットのWebブラウザ(Google Chromeなど)は、アクセスしたWebサイトのデータをキャッシュファイルに保存します。同じWebサイトに再びアクセスすると、保存したキャッシュファイルからデータを読み出すことで、初めてアクセスするときよりも高速で表示させることができます。
そしてこのアクセスにかかる時間を求める問題が出題されます。
アクセス時間の求め方
アクセス時間を求めるにあたって知っておきたい用語は、キャッシュメモリとヒット率です。
キャッシュメモリとは、主記憶装置とCPUの速度差を補うために用いる記憶装置のことで、1度読みだしたデータなどをキャッシュメモリに保存しておくことで処理速度を高速化するのが狙いです。
ヒット率とはキャッシュメモリの中に該当データがある確率のことです。アクセス時間とキャッシュメモリ・ヒット率の関係は以下の式で表されます。
実行アクセス時間 = キャッシュメモリのアクセス時間 × ヒット率 + 主記憶のアクセス時間 × (1 - ヒット率)
合わせて読みたい
-
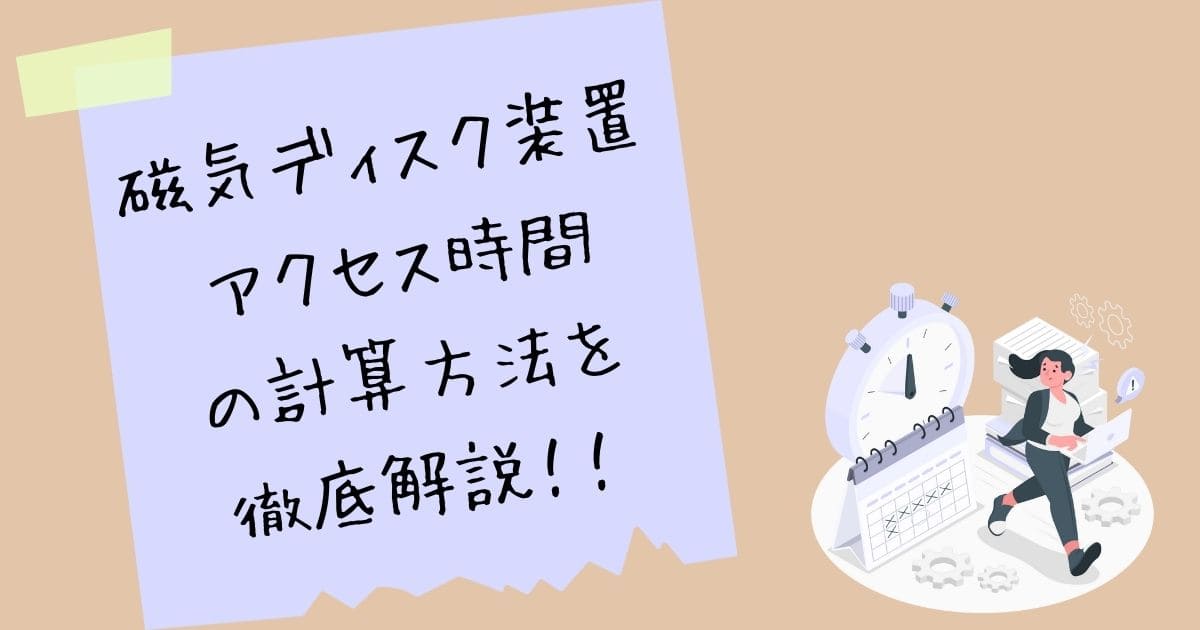
-
【磁気ディスク】平均アクセス時間や平均待ち時間の求め方を図解ありで徹底解説!
続きを見る
アクセス時間を求める過去問にチャレンジ
キャッシュメモリのアクセス時間及びヒット率と,主記憶のアクセス時間の組合せのうち,主記憶の実効アクセス時間が最も短くなるものはどれか。
出典:平成20年秋期 午前問19
解説)
「実行アクセス時間が最も短くなる」 というのは、「一番高速なのはどれか 」という問題です。
「実行アクセス時間 = キャッシュメモリのアクセス時間 × ヒット率 + 主記憶のアクセス時間 × (1 - ヒット率)」
この公式を覚えていれば、1つずつ計算してもいいですが、キャッシュメモリにデータがある方が高速化できるという特徴を覚えておき、キャッシュメモリと主記憶のアクセス時間が同じであれば、ヒット率が高いほど高速であるという特徴を思い出します。
つまり回答はイとエに絞られるため、実際に計算するのはこの2つだけでOKです。
イは 10 × 70% + 70 × (1 - 70%) = 7 + 21 = 28
エは 20 × 80% + 50 × (1 - 80%) = 16 + 10 = 26
よって答えは エ となります。
レジスタ容量や主記憶サイズを問う問題の解き方
基本情報技術者試験では、アドレスビット数や主記憶サイズに関する問題も頻出です。計算の型を覚えておけば、確実に得点につなげられます。
これらの問題は暗記よりも「公式の理解」と「単位変換の慣れ」が重要です。多くの場合、ビット数・バイト数・キロバイトなどの変換や、「2の何乗でいくつアドレスを表せるか?」といった2進数の理解力が試されます。
| 問題例 | ポイント |
|---|---|
| 16ビットのアドレスで表せる最大メモリ容量は? | → 2¹⁶バイト(=65,536バイト) |
| 32KBの主記憶装置を持つとき、アドレスビット数はいくつ必要? | → 2の何乗で32KBになるかを逆算(答え:15ビット) |
計算ミスを減らすには、公式の暗記だけでなく「どう変換すればいいか」の思考手順を理解することが鍵。苦手意識がある方は、動画講座(例:Udemyの計算問題講座)で視覚的に学ぶのもおすすめです。
最低限必要なメモリ容量を求める計算問題
表示解像度が1000×800ドットで、色数が65,536色(216色)の画像を表示するのに最低限必要なビデオメモリ容量は何Mバイトか。
ここで、1Mバイト=1,000kバイト,1kバイト=1,000バイトとする。
ア:1.6 イ:3.2 ウ:6.4 エ:12.8
この問題は、画像の表示に必要なビデオメモリ容量(=ピクセル数 × 1画素あたりのビット数)を計算する問題です。表示解像度とは「画面に表示されるドットの数(横 × 縦)」、色数とは「1画素を表現するのに必要な色の種類」です。
おすすめの学習方法5選
- 解像度(ピクセル数)横1,000 × 縦800 = 800,000ピクセル
- 色数 → 必要なビット数 65,536色 = 2¹⁶色 → 16ビットで表現できる
- 必要なビット数(合計)800,000ピクセル × 16ビット = 12,800,000ビット
- バイトに変換(8ビット = 1バイト)12,800,000 ÷ 8 = 1,600,000バイト
- Mバイトに変換(1,000,000バイト = 1 Mバイト と定義されている)1,600,000 ÷ 1,000,000 = 1.6 Mバイト
よって答えはア:1.6となります。
ハードウェア分野の効率的な学習法とおすすめ教材
「ハードウェアやコンピュータの構成要素が苦手で、いつも後回しにしてしまう…」そんな悩みを抱えているなら、学習方法そのものを見直すことが合格への近道です。
基本情報技術者試験のハードウェア分野は得点源にしやすい分野といわれている反面、苦手な人も多く、点数が安定しにくい分野です。だからこそ、自分に合った学習スタイルと教材を選ぶことが重要です。
基本情報技術者試験おすすめの学習方法
| 学習手段 | おすすめ度 | 特徴 | 向いている人 | 主なサービス例 |
|---|---|---|---|---|
| 本・参考書 | ・費用が安い ・自分のペースで進められる ・網羅性が高い | ・独学が得意な人 ・紙で学習したい人 | ・キタミ式 ・栢木先生 | |
| 動画講座(Udemy) | ・映像で理解しやすい ・1講座単位で学べる ・レビューが豊富 | ・図や動きで理解したい人 ・短期集中型 | ・Udemy ・YouTube | |
| オンライン通信講座 | ・カリキュラムが組まれている ・質問サポートあり ・スキマ時間に学べる | ・効率的に合格したい人 ・学習管理が苦手な人 | ・BizLearn ・スタディング |

それぞれの教材には特徴や向いている人のタイプもあわせて解説しているので、「結局どれを使えばいいのか分からない…」という方も、きっと自分に合った学習法が見つかるはずです。
オンライン通信講座【Bizlearn・スタディング】
基本情報技術者試験の過去問対策の中で、ハードウェアや計算問題に苦手意識があるのであれば、オンライン通信講座で体系的に学習するのがおすすめです。
基本情報技術者試験では、CPUやメモリ、レジスタといった専門用語がとても分かりづらく。その上計算問題が多く出題されるので、独学だと理解に時間がかかりがちですが、オンライン通信講座なら図解付きで視覚的に理解しやすく、わからないときは気軽に質問できるのでとても安心です。
おすすめのオンライン通信講座
| 講座名 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| Bizlearn | 講義+問題演習のバランスが良く、スマホ学習も可能 | ・科目A試験は免除して科目Bに専念したい人 ・復習型の学習に向いている |
| スタディング | 最短合格を目指すカリキュラム。合格者の声多数 | ・コスパ重視で学習したい人 ・時間効率を重視したい人におすすめ |
「独学に限界を感じている」「過去問が解けるようになりたい」という方は、体系的な学習ができるオンライン講座を活用することで、合格までの道筋がグッと近づきます。
関連記事:基本情報技術者試験に合格するためのオンライン講座おすすめ3選
動画教材【Udemy】
基本情報のハードウェアが苦手な人の中で、オンライン通信講座よりも安価に学習を進めたい人はUdemyの動画講座で見て覚えるもおすすめ。
テキストではCPU・メモリ・レジスタなどの仕組みがうまく理解できなくとも、動画であればイメージが湧いて理解しやすくなることがあります。さらにはUdemyならセール時は1,000円台で優良講座が購入でき、オンライン通信講座と比べても圧倒的にコスパが良いです。
おすすめのUdemy講座3選
| 講座名 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 参考書の著者直伝!【基本情報技術者試験 科目A】講座 | 擬似言語やアルゴリズム データ構造などを体系的に学べる 過去問ベースで解説も丁寧 | 試験範囲を広く網羅したい人 最短合格を目指す人 |
| 基本情報技術者試験 最速 合格講座 | C言語や配列 ポインタなど実装寄りの基礎から応用まで幅広く学べる | リスト構造の実装に不安がある人 言語を使って理解したい人 |
| ITパスポート+基本情報技術者を"理解しながら"学ぶ講座 | データ構造の前提となる IT基礎やネットワークを動画でやさしく解説 | 超初心者 まずはIT知識全体を把握したい人 |
「読んでもわからない」なら、見てわかる動画学習でハードウェアを得点源に変えるチャンスです。まずは気になる講座をチェックしてみましょう!
合わせて読みたい
-

-
Udemyで基本情報技術者試験合格を目指す!おすすめ講座5選!
続きを見る
参考書・問題集
ハードウェア分野の苦手意識を克服したいなら、自分の理解レベルに合った参考書や問題集を使って演習を重ねるのが効果的です。今使っている参考書で理解できないのは、初学者向けの参考書ではないのが原因かも。
特に、問題パートの解説が簡素すぎると、間違えた問題に対して理解ができないままモヤモヤが残りますよね。
勉強をするのに適している派閥として、動画派とテキスト派がいます。あなたがもし「動画よりも手元で学びたい」「パラパラめくりながら確認したい」のであれば参考書+問題集の併用が1番です。
上記3冊であれば初心者でもわかりやすく、解説重視で評判の高い参考書・問題集。あなたのレベルやパラパラ見てみたときのフィーリングを信じて1〜2冊に購入してみると、理解効率もグッと上がりますよ!
合わせて読みたい
-
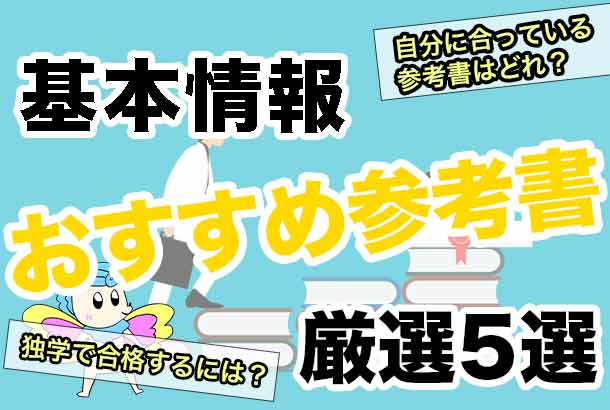
-
基本情報技術者試験おすすめ参考書10選|独学で合格するための最新版テキストを厳選!【令和7年度対応】
続きを見る
まとめ:
今回は、基本情報技術者試験(FE試験)で頻出のハードウェア分野について、CPUやメモリ、クロック周波数といったコンピュータの構成要素を図解とともに解説してきました。
「CPU=頭脳」「メモリ=作業机の広さ」など、イメージで覚えておくと、試験本番でも用語がスッと頭に入ります。また、科目A試験では「意味や役割」を問う知識問題に加え、クロック周波数・アクセス時間などの計算問題も高確率で出題されます。
この記事で紹介した内容は、どれも得点源に直結する重要ポイントばかりです。「理解はできたけど、演習が不安…」という方は、オンライン講座や動画教材を活用して、効率よく対策を進めましょう。
基本情報技術者試験おすすめの学習方法
| 学習手段 | おすすめ度 | 特徴 | 向いている人 | 主なサービス例 |
|---|---|---|---|---|
| 本・参考書 | ・費用が安い ・自分のペースで進められる ・網羅性が高い | ・独学が得意な人 ・紙で学習したい人 | ・キタミ式 ・栢木先生 | |
| 動画講座(Udemy) | ・映像で理解しやすい ・1講座単位で学べる ・レビューが豊富 | ・図や動きで理解したい人 ・短期集中型 | ・Udemy ・YouTube | |
| オンライン通信講座 | ・カリキュラムが組まれている ・質問サポートあり ・スキマ時間に学べる | ・効率的に合格したい人 ・学習管理が苦手な人 | ・BizLearn ・スタディング |
コンピュータ構成要素まとめ
- ハードウェアとは パソコン本体や付属品など、実際に触ることができる機械の部分
- CPU ➾ コンピュータの頭脳
- メモリ ➾ コンピュータの仕事能力
- クロック ➾ コンピュータが一定間隔で発生させることのできる電気信号
- クロック周波数 ➾ 1秒間に発生させることのできるクロック数
- キャッシュメモリ ➾ CPUとメモリの速度差を補うために用いる記憶装置